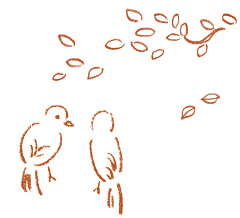
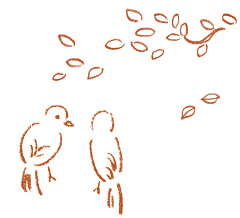
公開シンポジウム「超高齢社会のなかで地域ケア力を考える」
■日時:2013年11月9日(土)13:00~17:00
■会場:大阪市立青少年センターKOKO PLAZA 「エクスプレス・ココ」ホール
大阪市東淀川区東中島1-13-13 TEL.06-6370-5421
http://www.kokoplaza.net
■シンポジスト:
・佐藤伸彦(ものがたり診療所・医師)
「ものがたり在宅塾の現在」
・各地域での取り組み
藤本啓子(神戸)
岩切かおり(大阪)
林道也(京都〜岡山)
■シンポジウムの趣旨:政府は昨年「在宅医療・介護あんしん2012」という施策を打ち出し、「地域包括ケア元年」と位置づけ、年老いても住み慣れた地域で暮らし、最期を迎えられるよう、在宅医療・看護・介護の整備を進めています。しかし、地域・在宅での受け入れ体制が十分に整わないまま、早期退院を求められる高齢者と家族は困惑のなかにあるとも聞きます。そんななか、前回のシンポジウム(7月15日)では、「超高齢社会のなかで在宅での看取りを考える」と題して、在宅で死ぬことはどうすれば望ましいものになるのか、在宅で看取ることはどうすれば可能になるのか、を皆さんとともに考えました。しかし、言うまでもなく、在宅医療・看護・介護・看取りは、地域から孤立した閉ざされた自宅という空間でのケアを意味するのではなく、またそのような閉ざされたケアとしては不可能でもあり、在宅ケアは地域に根を張ったケアのネットワークのなかでこそ可能になるものであり、そのような言わば「地域ケア力」があれば、「老々介護」を続けることも「おひとりさま」を在宅で看取ることも可能となるものです。それでは、どのようにしてそのような地域に広がるネットワークとしての「地域ケア力」を育てることができるのか、あちこちで始まっている「地域ケア力」を育てる試みを紹介しながら、皆さんと一緒に考えたいと思います。
■参加費:無料
■お問い合わせ・参加申し込み……参加予約が必要です
はがき又はメールでお申し込みください
氏名、TEL、FAX、メールアドレスを明記願います
定員になり次第締め切ります。
満席となりお断りする場合にのみ、連絡いたします。
〒560-8532 大阪府豊中市待兼山町1-5
大阪大学文学研究科 臨床哲学研究室気付
「ケアの臨床哲学」研究会 宛
E-mail :yoshinokumano@gmail.com
■主催:「ケアの臨床哲学」研究会(大阪)
共催:患者のウェル・リビングを考える会(神戸)
〈ケア〉を考える会(京都〜岡山)
科研プロジェクト「定常型社会におけるケアとそのシステム」
昭和33年東京生まれ。
国立富山大学薬学部卒業後、同大学医学部卒業。
平成2年同大学和漢診療学教室の研修医を皮切りに、
成田赤十字病院内科、飯塚病院神経内科などを経て、
富山県砺波市 砺波サンシャイン病院で副院長として、
高齢者医療にかかわる。
市立砺波総合病院地域総合診療科部長、外来診療部内科部長を経て、
ナラティブホーム構想の提唱者として、さまざまな支援のもと、
医療法人社団ナラティブホームを平成21年4月に立ち上げ、
平成22年4月1日に「ものがたり診療所」を砺波市でオープン。
同診療所の所長を務める。
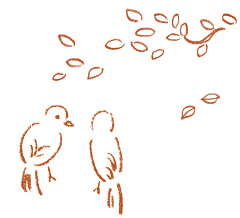
そして、そのものがたりは 多種多様です。
「ナラティブ」とは、英語で「物語」という意味です。
高齢の患者さんたちにも、今まで生きてきたその人だけの「物語」があります。
患者さん一人ひとりが持つ、かけがえのない「物語」を大切にし、
それを中心に医療を組み立てていくのが、
私たち「ナラティブホーム」です。
 寝たきりでコミュニケーションのとれない患者さんを目の前にしたとき、
寝たきりでコミュニケーションのとれない患者さんを目の前にしたとき、
「こんな状態で生きる意味があるのだろうか」と自問する人もいます。
しかし、私たちは、そうは考えません。
何も言わない患者さんがただ目の前に存在しているという事実こそが大切。
私たちに何を問いかけているのか、
患者さんの声に耳を澄ますべきなのです。
 患者さんの急逝、そこで医療が終わりになるわけではありません。
患者さんの急逝、そこで医療が終わりになるわけではありません。
患者さんの最後の生がどのようなものであったのかを、
医師が告別式のときに参列者に語ってもよいのではないか、と考えます。
最後の生に参与し、ご家族とともに語らう時、
「ひとつの物語」が完成するのではないでしょうか。
 「物語」の医療を進めていくには、医療側と患者側、
「物語」の医療を進めていくには、医療側と患者側、
そして地域の理解と協力が不可欠です。
家庭のような病院の運営を実現するために、
私たちは「ものがたり診療所」として新たな第一歩を踏み出します。
ものがたり診療所所長 佐藤 伸彦